~行政書士が解説する、現場で本当に指導されるポイント~
こんにちは、行政書士の櫻井です。
宅地建物取引業(宅建業)の免許申請を進めるうえで、最初につまずきやすいのが「事務所の要件」、特に**事務所の“独立性”**です。
今回は、これから宅建業免許を取得しようとする方向けに、「ここを見落とすと指導が入る」「実際に確認されることもある」といった実務のリアルな情報をお伝えします。
■ そもそも「独立した事務所」とは?
宅建業の免許要件として、「専用の事務所を設けていること」が必須です。
この“専用”には、以下の2つの意味が含まれます:
- 他業種や他社と共用していないこと
- 個人の自宅や居住空間と明確に区別されていること
つまり、「名ばかりの事務所」や「他社と机を並べただけのスペース」は、独立性なしとみなされ、不許可や是正指導の対象になることがあります。
■ よくあるNG例:「名義や表示のダブり」に要注意
私が実際に見てきた中で、指導が入ったケースとして多いのが以下のようなものです:
- ポストに他社の名前も書かれている
→ 実質的に“兼用”と判断されることがあります。 - 看板や表札に複数の業者名が併記されている
→ シェアオフィス、レンタルオフィスでは特に注意が必要です。 - 内部が仕切られていない、間仕切りだけでつながっている
→ 個別の施錠設備がない、共通電話を使っている等もNGになることがあります。
こうした“ちょっとした名義の重なり”であっても、「宅建業者が単独で独立して業務できる体制がない」と判断されることがあるため、非常に重要なポイントです。
■ 行政庁は「登記簿」や「契約書」もチェックする?
はい、します。
宅建業の免許審査においては、次のような資料を通じて事務所の実態が確認されます:
- 事務所として使っている物件の賃貸借契約書
- 使用許諾書(所有者が他人の場合)
- 法人の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 会社の定款
- 現地写真(室内・看板・入口・郵便受けなど)
特に法人の登記簿上の所在地と、宅建業免許の申請先に記載する所在地が異なる場合は、注意が必要です。
「登記上はA市、事務所はB市」というケースでは、「実際に営業の実態があるのか?」と疑義を持たれ、追加資料の提出や現地調査が入ることもあります。
また、申請後に管轄の宅建指導課等から「事務所の写真を再提出してください」「ポストの表示を撮り直してください」といった是正指導が入るのも珍しくありません。
■ シェアオフィス・自宅兼用はOK?NG?
結論から言えば、状況によります。
- シェアオフィスの場合:
→ 完全に間仕切られ、独立した鍵付きスペースであり、他業者との共用部分(受付・ポスト等)がない状態であれば許可される可能性があります。
→ しかし現実には、要件を満たすシェアオフィスは少ないです。 - 自宅兼用の場合:
→ 明確に生活空間と業務スペースが区分されていること(間取りや入口が別等)が条件になります。
→ 室内写真の提出で「自宅のリビングの一角」と判断されると、独立性がないと見なされる場合があります。
■ 行政書士からのアドバイス:まず“現地写真”と“契約書”を確認
宅建業免許のご相談を受けた際、私がまず確認するのは以下の2点です:
- 物件の賃貸契約書や登記簿の所在地
- 実際の事務所の外観・内観写真(ポスト・看板・机など)
これらをチェックすることで、事前に「このままだと指導が入りそうか」「別途使用許諾書が必要か」「表示を直す必要があるか」など、先回りして対応できます。
■ まとめ:事務所要件は、免許審査の最初のハードル
宅建業免許の申請は、書類作成もさることながら、「事務所が要件を満たしているかどうか」が大きなカギになります。
形式だけでなく、実際の使用実態・表示・名義など“細かいところまで”見られるため、準備不足だと申請後に足止めされてしまうことも。
不安な方は、行政書士に事前に事務所写真や書類を見せてアドバイスを受けることをおすすめします。
宅建業免許の取得をお考えの方へ
当事務所では、初回相談は無料で対応しております。
「事務所の条件が不安…」「シェアオフィスだけど大丈夫?」といったご相談も歓迎です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
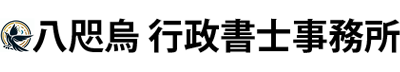


コメント